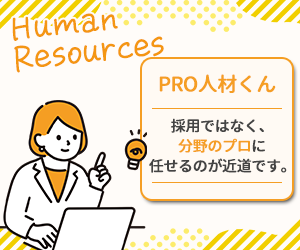「営業はしたいけど、アプローチする相手が見つからない」
日々の業務に追われて、“リストが作れない”営業現場のリアル。新しいサービスを広げたい。営業チームをもっと動かしたい。
これまでの展示会や飛び込み、紹介に頼らず、自分たちで新しいお客さまを見つけていきたい。
でも現実はどうでしょうか?
「手元に使える営業リストがない」
「どこに営業をかければいいのか見当もつかない」
「これまで使い古された営業リストしか残っていない」
「調べる時間もないし、そもそもどこから始めたらいいのか分からない」
営業を“始める前”で立ち止まってしまう。
そんな企業が今、驚くほど増えています。
営業活動が止まってしまう“営業先リストの壁”
「どこに営業をかければいいのか分からない」
「手元の訪問リストが古くて、そもそも連絡がつかない」
「社内で営業先を調べてリスト化する時間も人手もない」
そんな悩みを抱えている営業担当者は、実は少なくありません。
営業活動の“はじめの一歩”が踏み出せないことが、営業チーム全体の動きを止めてしまっているのです。
実際に、営業現場ではこんな課題が起きています:
- 営業リストの作成に週10時間以上かけている担当者は57.8%
- そのうちの約7割が「作ったリストの精度に不満」と回答(Timers Inc.「営業リスト作成の基本知識」)
- 営業リストを手作業(Excelなど)で作っている企業は52.6%
- 成果につながらないリストづくりに「やりがいを感じない」と答えた営業担当者は41.2%(Salesforce営業現場調査)
つまり、“使える営業リストがない”ことで:
- 調べてばかりで営業の時間が削られる
- 電話もメールも反応がない
- 担当者自身も「このやり方でいいのか?」と感じながら手を動かしている
こうした状態が、営業成果の低下だけでなく、現場のモチベーション低下にもつながっているのです。
さらに、コロナ禍以降、飛び込みといった従来型の新規開拓チャネルが減ったこともあり、「自分たちで営業先を見つけていく力」が求められる今、営業先のリスト化の“仕組み”を整えられていない企業は、思うように動けなくなっている現状があります。
営業が機能しないのは、「仕組みの古さ」にある
営業リストがない、作っても成果につながらない。
こうした状況を根本的に生んでいるのは、営業活動の仕組みそのものが“今の時代に合っていない”ことにあります。
属人化と「経験頼み」のターゲティング
多くの営業現場では、
「●●さんの知り合いに紹介をもらって…」
「この展示会に出ていた企業なら見込みがありそう」
といった、個人の勘や過去の感覚に頼ったアプローチがいまだに主流です。
こうした方法は、一部のベテラン営業には通用しても、再現性が低く、組織全体の成果にはつながりにくいのが実情です。
情報が“整備されていない”ままスタートする現場
リストを作るにも、情報の収集・整理がバラバラ。
営業チームが顧客情報をどこからどう集め、どう蓄積し、どんな基準で分類しているかが、社内で共有・仕組み化されていないというケースが大半です。
そのために、
- 情報の鮮度が低い(移転済・担当者変更などが反映されない)
- アプローチ先に一貫性がなく、ムダ打ちが増える
- 営業会議で「誰に営業してるの?」が噛み合わない
といった“仕組みの弱さ”による営業の空回りが起こっています。
顧客の切り口が「ザックリしすぎている」
業種・地域といった表面的な属性だけで営業先を選んでいる場合も少なくありません。
たとえば「製造業」と言っても、
部品メーカー、機械設備業、OEM、自社ECあり/なし、BtoBかBtoCか、などでニーズは大きく異なります。
こうした細かい「セグメントの視点」がないまま営業を始めてしまうと、
“誰に対して、何の価値を届けたいのか”が曖昧な営業になり、成果につながりません。