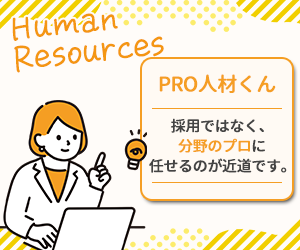「健康も含めて自己管理ができて一人前」――そうした価値観が、今なお多くの職場に残っています。
体調を崩しても「自己責任」として済まされ、誰にも頼れないまま働き続ける。そんな状況に、違和感を覚えている人も多いのではないでしょうか。
実際、忙しさのあまりコンビニや外食に頼った食生活を続けた結果、体調を崩してしまう社員も少なくありません。
それでも、企業として健康支援に踏み出すには「コストや手間がかかる」「社員に利用されるかわからない」といった不安が立ちはだかります。
また、昼休みの時間帯がバラバラだったり、部署を越えた交流の機会が限られていたりと、“孤食”のまま黙々と食事をする社員も増えています。
栄養の偏りだけでなく、気持ちのリフレッシュや人とのつながりが得にくいことも、見過ごされがちな職場課題のひとつです。
社員の健康を、個人だけに委ねてしまわないために。
日常に自然と溶け込む、さりげない支援のかたちが、いま求められています。
忙しさの陰で見過ごされる、社員の食生活──そのままで大丈夫?
“社員の健康”を支えるのは、食のインフラかもしれない
社員の健康支援や食生活改善といった課題に対して、手軽に取り組める方法はないのでしょうか。
その一つの答えが、「オフィスおかん」が提供する“置き型社食”という選択肢です。
オフィスおかんは、冷蔵庫と電子レンジを設置するだけで導入できる、簡易社食サービス。
1品100円(税込)という手頃な価格で、管理栄養士監修の健康的なお惣菜を24時間いつでも利用できます。
オフィス内にあることで「忙しくても、すぐ手に取れる」「誰かと一緒に食べるきっかけになる」といった、日常の中で自然に健康を支える仕組みとして、企業から高く評価されています。
オフィスおかんの特長:
- 導入がかんたん:冷蔵庫と電子レンジを設置するだけ。大がかりな設備投資は不要
- 高コスパな健康支援:1品100円(税込)でバランスの取れた惣菜が提供可能
- 時間・働き方を問わず使える:昼休みの時間がずれても、いつでも利用OK
- コミュニケーションのきっかけにも:同じ場所・時間で食事をする場が生まれる
- 健康経営・福利厚生としても機能:制度のアピールやエンゲージメント向上に
日々の“食”を通じて、社員の健康と職場の空気を少しずつ変えていく。
それが、オフィスおかんの提案する「無理なく続けられる福利厚生」のかたちです。
実際に動き出した企業では
サービス業・少人数規模|健康的な食事提供と社内コミュニケーションの促進
少人数のオフィスで「外食やコンビニ頼りの昼食が多い」という課題を抱えていた企業では、「オフィスおかん」の導入によって、ランチタイムに自然と社員が集まり、会話が生まれるように。
一人暮らしの社員が多く、栄養バランスの良いお惣菜が手軽に食べられる点も好評でした。
“おかんの味”のような、優しく飽きのこないメニューが、毎日の健康習慣として定着しつつあります。
※参考:導入事例|AZUMA
建設業・中小規模|現場で働く従業員の食事環境を改善
昼食が不規則になりがちな現場作業員のために、社内に「オフィスおかん」を導入した企業では、冷蔵庫から手軽に健康的なお惣菜を選べることで、食生活が改善され、社員の健康意識も高まったといいます。
また、食事をきっかけとした世代を超えたコミュニケーションも生まれ、現場の雰囲気が和らいだとの声も。
サービス業・25名規模|“美味しくて便利”が定着する福利厚生に
健康経営の一環として「社員が栄養バランスを意識できる仕組みを取り入れたい」と考えていた企業が、「オフィスおかん」を導入。
昼食をコンビニで済ませていた社員たちが、毎日のようにお惣菜を利用するようになり、「美味しい」「便利」といった声が定着。
社員の健康意識と満足度の両面に好影響があったといいます。
「ちょうどいい福利厚生」が、働く環境を静かに変えていく
「健康支援をしたい気持ちはある。でも、予算も手間も限られている」
そう感じていた企業が、“ちょうどいい”福利厚生として選んでいるのが「オフィスおかん」です。
冷蔵庫と電子レンジを設置するだけで始められ、1品100円(税込)という続けやすさ。
社員の健康意識が自然と高まり、コミュニケーションのきっかけも生まれる。
派手な制度ではないかもしれませんが、“続けられる仕組み”として確かな手応えがあります。
「うちの会社でも使えるかも」と思ったら、まずは資料を見てみてください。
具体的な導入方法や、他社の活用事例もご覧いただけます。